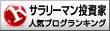【要約・感想】『ゆるストイック』(佐藤航陽)への違和感〜「ゆるさ」が利己に走る諦めになっていないか〜
佐藤航陽さんの『ゆるストイック ノイズに邪魔されず1日を積み上げる思考』を読みました。 帯に「大谷翔平、井上尚弥、藤井聡太……なぜ、「ストイック」かつ「ゆるく」自分に向き合い続けるのか」と書かれています。 ここで名を挙げられている方々は「ゆるく」と言われて嬉しいのだろうかと、その名にあやかりつつ勝手なレッテルを貼るおこがましさを、商業出版社には感じます。 しかしながら、矛盾や仕方なさを抱えることを肯定する論調が好きなので「ゆるさ」と「ストイック」をどう両立させるのだろうかと、本書を手に取りました。 要約 コロナ前後で世界は一変した。多様性重視で他者への干渉は躊躇され、指導はコストと見なされる。陰で努力できる人とできない人で二極化が進んでいる。その中で、成功を収めるには基盤を最大限に活用しながら独自性を発揮することが重要だ。ニッチな世界から活動を始め、試行回数を増やそう。変化に柔軟であろう。 感想 良いことも書かれているのですが第6章がものすごくイマイチで、読後感はあまり良くなかったです。詳細は後述します。脳科学的な記述が散見されるのも、樺沢紫苑さんの本のようなウケを狙いすぎている感じがして、私はやや苦手でした。。。 良かった部分 アンラーニング ケチなので「アンラーニング」という言葉がイマイチ理解できていませんでした。せっかく学んだことを捨てるなんて勿体ない、知識は積み上げて行くものだ、と思っていました。 しかし著者が日々の情報源を変えることで、それまでなぜそんなことを気にしていたのだろう、と考えが変わったと書かれていました。 アンラーニングとはこれまでの価値観、固定観念から解放されよう、ということなのですね。その意味でもstudyingではなくlearningなのでしょうか。これまでの理解が誤っていたことを知りました。 自分の周りにいる5人の平均が自分 会社のキャリア研修でもこれを聞き、なるほどと思った部分でした。 この本ではそれを客観的にコントロールするために、「自分メンテナンス時間」として振り返りの時間を設け、理想の5人を考えることを推奨します。 たしかにいいかもしれません。先ほどの情報源を変える話もそうですが、何の価値観に侵されているのか、自分はどうありたいのかは、自分で手綱を握っておく必要があります。 ...