【感想】『暇と退屈の倫理学』國分功一郎
久々の人文系読書。株に関心が出て実学に寄っていたので、ありがたいゆり戻し。行ったり、来たりすることが大事だと思い出した。
「好きなこと」とは何か?
人類は豊かさを目指してきた。なのになぜかその豊かさを喜べていない。余裕のある社会になって人々が時間を費やす「好きなこと」は、必ずしもそれまで「願いつつもかなわなかったこと」ではない。
暇と退屈の原理論
パスカルは人間は<欲望の対象>と<欲望の原因>を取り違えているという。気晴らしのウサギ狩りはウサギが欲しいから狩りをするのではない。ウサギ狩りに行く人に、ウサギを手渡しても嫌な顔をされるだけだ。
ラッセルは『幸福論』で、20世紀初頭のヨーロッパでは、すでに多くのことが成し遂げられていて、これから若者たちが苦労してつくり上げねばならない新世界などもはや存在せず、彼らは不幸である。それに対し、ロシアや東洋諸国ではまだこれから新しい社会を作っていかねばならないから、若者たちは幸福であると主張した。
しかしこの「新世界の建設」も「ウサギ狩り」と変わらない。また現代のそれなりに裕福な日本社会に生きる若者を、発展途上国で汗水たらして働く若者たちと比べて、「後者のほうが幸せだろう」と言うのに等しい。不幸への憧れを作り出す幸福論はまちがっている。
暇と退屈の系譜学
<定住革命>私たちは定住生活を前提として、遊動生活について価値判断を行っているが、やむを得ず定住化したと、考え直す。稲作到来以前に定住生活は始まっており、食料生産は定住生活の結果であって原因ではない。中緯度地域における温帯森林環境の拡大により狩猟が困難になり、貯蔵が必須の条件となった。貯蔵は移動を妨げ、定住を余儀なくされたと考える。持て余した能力を別の場面で発揮することが、「文明」を発生させた。
暇と退屈の経済史
20世紀の大衆社会では、ブルジョワジーのみならず大衆、労働者に余暇(レジャー)の権利が与えられた。フォードは生産性を向上するために労働者をおもんぱかった。その逆ではない。フォードは労働者の労働時間を制限し、十分な休暇を取ることをもとめた。一方、労働者が休暇中に何をしているのかを探偵やスパイに調査させていた。労働者も禁酒法に賛成していた。
こうしてレジャー産業が誕生する。レジャー産業の役割とは、何をしたらよいか分からない人たちに「したいこと」を与えることだ。レジャー産業は人々の欲求や欲望に応えるのではない。人々の欲望そのものを作り出す。土曜日のテレビでは、日曜日に時間的・金銭的余裕をつぎ込んでもらうための娯楽の類を宣伝する番組が放送されている。
ガルブレイスは消費者主権モデルの崩壊を指摘しながら、「新しい階級」の拡大が社会の目標だとする。それは「仕事こそが生き甲斐だ」と感じる人々の層である。しかし「仕事が充実するべきだ」という主張は、仕事においてこそ人は充実していなければならないという強迫観念を生む。人は「新しい階級」に入ろうとして、あるいは、そこからこぼれ落ちまいとして、過酷な競争を強いられる。
新しい階級の子どもたちは小さい頃から、満足の得られるような職業――労働ではなくてたのしみを含んでいるような職業――をみつけることの重要性を念入りに教えこまれる。新しい階級の悲しみと失望の主な源泉の一つは、成功しえない息子――退屈でやりがいのない職業に落ち込んだ息子――である。こうした不幸に会った個人――ガレージの職工になった医者の息子――は、社会からぞっとするほどのあわれみの目でみられる。
暇と退屈の疎外論
ボードリヤールは浪費と消費を区別する。浪費はどこかでストップする。しかし消費は止まらない。消費の対象は物ではなく、観念や意味だからだ。消費社会は、私たちが絶えざる観念の消費のゲームを続けることをもとめる。ガルブレイスが歓迎した仕事に生き甲斐を見出す階級の誕生も、消費の論理を労働にもち込んでいるにすぎない。彼らが労働するのは、「生き甲斐」という観念を消費するためなのだ。
暇と退屈の哲学
ハイデッガーは退屈を三つの形式に分ける。第一形式は「何かによって退屈させられること」、第二形式は「何かに際して退屈すること」。ただし第二形式では、パーティーに際して退屈しているが、実は同時にそのパーティーが気晴らしである。退屈と気晴らしとが独特の仕方で絡み合っている。そして第三形式は「なんとなく退屈だ」である。
暇と退屈の人間学
ここでユクスキュルの「環世界」が登場する。人間が頭のなかで抽象的に思い描く「世界」(環境)は虚構である。それぞれの生物はそれぞれの環世界を生きている。ダニはダニの。森で森林浴をしようとする散歩者、狩りをする猟師、森林の状態を検査する森林検査官。彼らは一つの同じ森を同じように経験するだろうか。
一つの環世界から別の環世界へと移行することの難しさについてユクスキュルは盲導犬を挙げる。訓練を受けた盲導犬がすべて盲導犬としての役割を果たすようになるわけではないのは、犬が生きる環世界のなかに、犬の利益になるシグナルではなくて、盲人の利益になるシグナルを組み込まなければならないからである。要するに、その犬の環世界を変形し、人間の環世界に近づけなければならないのだ。
人間はその他の動物とは比べ物にならないほど容易に別の環世界へと移動する。宇宙物理学について何も知らない高校生でも、大学で四年間それを勉強すれば、高校のときとはまったく違う夜空を眺めることになるだろう。作曲の勉強をすれば、それまで聞いていたポピュラーミュージックはまったく別様に聞こえるだろう。
それだけではない。人間は複数の環世界を往復したり、巡回したりしながら生きている。たとえば会社員はオフィスでは人間関係に気を配り、書類や数字に敏感に反応しながら生きている。しかし、自宅に戻ればそのような注意力は働かない。子どもは遊びながら空想の世界を駆け巡る。彼らの目には人形が生き物のように見えるし、いかなる場所も遊び場になる。しかし学校に行ったら教師の言うことに注意し、友人の顔色に反応しながら、勉強に集中しなければならない。
人間が極度に退屈に悩まされる存在であるのは、人間は一つの環世界にひたっていることができない、とどまっていられないからである。環世界を容易に移動できることは人間的「自由」の本質なのかもしれない。しかし、この「自由」は環世界の不安定性と表裏一体である。何か特定の対象に<とりさらわれ>続けることができるなら人は退屈しない。しかし、人間は容易に他の対象に<とりさらわれて>しまう。
暇と退屈の倫理学
ハイデガーは決断を推奨するが、決断という「狂気」の奴隷になることに他ならない。第三形式と第一形式は最終的に区別できない。「なんとなく退屈だ」の声が途方もなく大きく感じられるとき、人間は第三形式=第一形式に逃げ込む。仕事・ミッションの奴隷になることで安寧を得る。
「資格をとっておけば安心だ」という声に耳を傾けていれば、苦しさから逃れられる。しかも、世間からは「一生懸命頑張っているね」と褒めてもらえる。というか、周囲は褒める以外にない。それは、好きで物事に打ち込むのとは訳が違う。自分の奥底から響いてくる声から逃れるために奴隷になったのだから。
おそらく多くの場合、人間はこの声をなんとかやり過ごして生きている。そのために退屈と気晴らしとの混じり合いのなかで生きている。そうして「正気」の生を全うする。人間の生徒は退屈の第二形式を生きることである。
環世界論の考え方から言えば、習慣を創造するとは、周囲の環境を一定のシグナルの体系に変換することを意味する。毎日、目に入ってくるすべてのものに反応しているととても疲れてしまう。人間はものを考えないですむ生活を目指している。
ドゥルーズは、人間がものを考えるのは、仕方なく、強制されてのことだという。「考えよう!」という気持ちが高まってものを考えるのではなくて、むしろ何かショックを受けて考える。そのショックのことを「不法侵入」とも呼んでいる。
世界を揺るがすニュースでもいい、身近な出来事でもいい、芸術作品でもいい、新しい考えでもいい。環世界に「不法侵入」してきた何らかの対象が、その人間を摑み、放さない。その時、人はその対象によって<とりさらわれ>、その対象について思考することしかできなくなる。
考えるとは何かによって<とりさらわれ>ることだ。そして、衝動によって<とりさらわれ>て、一つの環世界にひたっていることが得意なのが動物であるのなら、この状態を<動物になること>と称することができよう。人間は<動物になること>がある。
人間は自らの環世界を破壊しにやってくるものを、容易に受け取ることができる。自らの環世界へと「不法侵入」を働く何かを受け取り、考え、そして新しい環世界を創造することができる。この環世界の想像が、他の人々にも大きな影響を与えるような営みになることもしばしばである。たとえば哲学とはそうして生まれた営みの一つである。
結論
際限のない消費によって満足が遠のき、退屈が現れる(疎外)。物を受け取れるようになることが、贅沢への道を開く。ラッセルは「教育は以前、多分に楽しむ能力を訓練することだと考えられていた」と述べている。訓練が必要なのは「教養」を必要とするいわゆるハイカルチャーの娯楽だけではない。食のように身体に根ざした楽しみも同じく訓練を必要とする。
楽しむことは思考することにつながる。楽しむことも思考することも、どちらも受け取ることである。人は楽しみ、楽しむことを学びながら、ものを考えることができるようになっていく。どんなにすばらしいものであっても、誰もがそれにとりさらわれるわけではない。ならば自分はいったい何にとりさらわれるのか? 人は楽しみながらそれを学んでいく。
ドゥルーズは、「なぜあなたは毎週末、美術館に行ったり、映画館に行ったりするのか? その努力はいったいどこから来ているのか?」という質問に「私は待ち構えているのだ」と答えた。ドゥルーズは自分がとりさらわれる瞬間を待ち構えている。そして彼はどこに行けばそれが起こりやすいのかを知っていた。
自分にとって何がとりさらわれの対象であるのかはすぐには分からない。そして、思考したくないのが人間である以上、そうした対象を本人が斥けていることも十分に考えられる。しかし、世界には思考を強いる物や出来事があふれている。楽しむことを学び、思考の強制を体験することで、人はそれを受け取ることができるようになる。<人間であること>を楽しむことで、<動物になること>を待ち構えることができるようになる。
何かおかしいと感じさせるもの、こういうことがあってはいけないと感じさせるもの、そうしたものに人は時折出会う。自分の環世界ではあり得なかったそうした事実を前にして、人は一瞬立ち止まる。そして思考する。しかし、それを思考し続けることはとても難しい。なぜなら、人は思考するのを避けたいからである。けれど、<動物になること>をよく知る人なら、何かおかしいと感じさせられるものと受け取り、それについて思考し続けることができるかもしれない。そして、そのおかしなことを変えていこうと思うことができるかもしれない。(中略)退屈と向き合う生を生きていけるようになった人間は、おそらく、自分ではなく、他人に関わる事柄を思考することができるようになる。それは<暇と退屈の倫理学>の次なる課題を呼び起こすだろう。
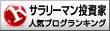
コメント
コメントを投稿