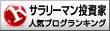【初心者投資ブログ】2025年1月の投資振り返り(投資1ヶ月目)

株式投資を始めてみる! 早速ですが2025年から株を始めてみました。今のところ楽しいです。はじめに今感じているメリットを挙げてみます。 投資信託から1年、株式投資に挑戦 頑張って稼いだお金が減るなんて絶対にあり得ない!と銀行預金しかしていなかったが、2024年にNISAで投資信託を始めてみると、労せず大金が手に入ることに驚いた。これに味をしめた。 明日が楽しみになった! また変わり映えのしない毎日に飽きてきて、何か違うことをしてみたいと思っていた。株を始めてみると毎日、明日はどうなるのだろう?これからどうなるのだろうか?と、未来、明日が楽しみになった! 政治・経済ニュースが自分ごとになった アメリカ大統領や日銀など生活と遠いところにあったイベントが、自分ごととして経験されるようになった!これは面白い。始めて良かったと思っている。 2024年成長投資枠で購入した240万円分の投資信託を売却 これについては議論の余地があるところでしょう。私は今年は2024年ほどはS&P500の投資信託で儲からないんだろうなと思いました。ですので、ここで利確してしまいそれを元手にもっと儲かりそうなものに投資したほうが良いのではないかと思ったのです。 また若い今のほうがこの金額が大金であり、嬉しく思えると考えたのです。そしてそもそも5年で1800万円をストレートに埋められるほどお金を持っておりません。翌年には枠が復活するのですから、一気に240万円売却してしまいました! 2025年の成長投資枠を埋める そして2025年の成長投資枠も埋めました。2024年はみんな大好き「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」に加えて、不安だったのでオルカン、と思いきや少し偏屈な部分が出て、別の運用会社にしようと思い「世界経済インデックスファンド」と半々にしていました。 オルカンは辞めました 実績はS&P500が世界経済インデックスファンドの約2倍でした。240万すべてS&P500にしていれば。。。という思いが頭をよぎります。電車の中の広告で「世界経済インデックスファンド」の広告を見ていた安心感から買ってしまいましたが、そういう広告宣伝に力を入れているものはあんまり良くなかったりするケースもあると思い起こされます。 ...