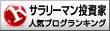【要約&感想】『孤独と不安のレッスン』鴻上尚史

東畑開人さんの『聞く技術聞いてもらう技術』の中で、「孤立」と「孤独」という言葉が出てきた。「孤独」についてはこの本が欠かせない。再読した。 本当の孤独とは 孤独になることで自分が「本当は何をしたいのか?」「本当は何を考えているのか?」を知ろう。しかし部屋に一人でも、メールやチャットで盛り上がっている時は「本当の孤独」ではない。「本当の孤独」とは、自分とちゃんと対話することだ。まずは恥ずかしくない孤独を体験してみよう。浜辺でぼーっと考えるのは一人が様になる<個人的にはファミレスで作業するのもおすすめ。ソロ活>。 思い込みから逃れる 「一人であること」が苦しいのではなく、「一人はみじめだ」という思い込みが苦しいのだ。『禁煙セラピー』という本の次の文章が紹介される。思い込みの力は大きい。 ニコチンが切れるとみんなイライラし始める。夜中、タバコがなくなると、みんな、もうどうしていいか分からなくなる。それはニコチンの禁断症状が強いからだと言われている。でも、寝ていてニコチンが切れたからといって目が醒めた人はいない。でも、コカインやLSDは、禁断症状で目が醒める。つまり、ニコチンの禁断症状は、じつは、とっても弱いものなんだ。ニコチンが切れても、目が醒めないんだから。じゃあ、何故、夜中にタバコが切れると絶望的な気持ちになるのか? それは、ニコチンの禁断症状は強いもんだという思い込みがあっただけなんだ。思い込みだから、それをやめれば、すむだけの話なんだ 深呼吸して体の重心を下に 焦っている人は体の重心が上になり、腰が引け、頭や胸を突き出して動くという。一方で落ち着いた人は、どっしりと腰の辺りで動いている感じがする。丹田と呼ばれるおへそから握り拳ひとつ下の部分に集中してみよう。息を深く吸って、丹田あたりに入れると意識してみよう。 日本人と『世間』 村八分という言葉があるように、日本社会において世間は絶対だった。しかし明治政府は国家を強くするために村落共同体の力を弱め、世間ではなく天皇が神だと設定した。このため『世間』の力は中途半端に壊れているが、日本人にとって世間は未だ神様であるから、みんなが「ラーメンが食べたい」というなら、カレーを食べたくても「わたしも」と言う。 また世間様をなくしてしまうと、欧米人が「それは神が許さない」と言えばすむことを、ひ...